「ラーニングフォーラム2010」を開催いたしました。多くのお客様にご参加いただき、大変好評の後に終了することができました。
内容について、報告いたします
| 開 催 日 | 2010年7月21日(水) 13:00~17:30 |
| 開催場所 | 福岡国際会議場 501会議室 |
| 講 師 | 原口泉様(鹿児島大学 法文学部教授)
増田弥生様(前ナイキアジア太平洋地域 人事部門長) |
| 音 楽 | 涼恵様 |
13:00~ オープニング〜ラーニング・システムズ株式会社 代表取締役社長 高原 要次

ラーニング・システムズの企業理念、大切にしていること
“学習を通して成長し、人の役に立ち、人生を楽しむ”
●ラーニング・フォーラムのコンセプト
・「成長曲線」今までの延長線上に未来はなく「変わる」事が必要
・「学習する組織」組織が学習して発展するためのお手伝い
●激動の時代の”人”づくり
・時代・・経験・・歴史・・について考え、現在を視る
・日本・日本人、グローバル・・マーケットは広がっている。世界で通用する日本人という視点を持つ
・リーダー・リーダーシップ・・日本人だから発揮できることとは何か
こういった視点で本日は皆さんと考えていきたい
13:15~ 幕末・維新のリーダーたち~組織を動かし時代を動かす~
鹿児島大学法文学部教授原口 泉様

思いつきを理論化する、そして実行するには段取りが重要となってくる。段取りをする上で重要なのは、リーダーの存在である。リーダーに求められる役割や能力について、幕末の人物の生き様から学ぶ
●組織を動かすこと=人の心を動かすこと
指示・命令形では、人の心を動かすことはできない。リーダーには「人の心を動かす」ための情熱が必要である。
●明確な目標 ×情熱(パッション)
西郷隆盛、大久保利通らは「倒幕」という目標を掲げ薩摩藩を動かし、着々と実現に向けて行動していた。「倒幕」という目標達成のために何をどうするのか、そのコンテンツを伝えようという情熱(パッション)があり、実際に周りを動かしていった。
●「夢」を持ってリスクをおかす
「夢」つまり「ビジョン」実現にためには、できないことを考えるのではなく、できることを考える。特に変革期においては、リスクをおかすことを厭わず、まず行動することが重要。薩摩の郷中教育においては「あとで考える」は通じない。即考える、即決断することが徹底されている。
幕末において坂本龍馬が果たした役割は大きい。「他を排除しない生き方」を実践した日本で初めての人物であり、指示・命令形ではなく人の心を動かす情熱を持ったリーダーであった。
「世の人は我を何とも言わば言え、我がなすことは我のみぞ知る」とは己の信念を貫いた龍馬らしい言葉といえる。
14:55~ グローバル・リーダー ~日本人が世界でできること~
前ナイキ アジア太平洋地域 人事部門長 増田弥生様

会社員生活が楽しい!と思える組織とは?社員がイキイキと働くためにリーダーが果たす役割とは? 自身の経験・キャリアを踏まえてのディスカッション形式での講演。
●リコーの10年 <ビジネスパーソンとして成長した10年>
ジョイントベンチャーの設立から精算をまでを経験したことで「企業は組織や人の能力を高める」ことを考えるべきと思うようになった。現場を良く理解できた10年だった。
●リーバイスの10年 <専門家になるための10年>
組織開発の仕事を徹底的に学び実践した。現場を知っていることが非常に役に立った。リーダーとして人を動かしその気にさせるためには、命令形ではなく横並びで一緒に目指すことが重要である。
★グローバルで活躍するためには「日本人であること」に誇りと自信を強く持ち、100%自分自身であることで世界に貢献する、とこのころから強く感じるようになった。また、グローバルであるためには、日本と海外という考え方ではなく地球規模で考える視点を持つことが重要である。
●ナイキの10年 <仕事のプロとしての10年>
リーダーとしてまず初めにビジョンを示した。その後も常にビジョンを示してチーム(組織)の道筋を示し続けた。
20人いたら20通りの言い方ができること、これがグローバルには欠かせない。そのためにはチームのメンバーは、C3PO(忠実なしもべ)ではなく、ヨーダ(力あるコーチ)でなければならない。(スターウォーズは万国共通だから)
日本人・日本企業にはリーダーシップ・アイデンティティが欠如していると感じる。自分は(組織は)どうしたいのかというビジョンが欠けていたり、人から学ぼうという姿勢や貪欲さが少ないように感じる。リーダーシップはリーダーだけのものではない。一人ひとりが発揮するものである。
16:10~ ラーニング・システムズからのお知らせ
ラーニング・システムズ株式会社 営業部長 高山有朋

ラーニング・システムズの近況について3つの視点で紹介
●リコーの10年 <ビジネスパーソンとして成長した10年>
ジョイントベンチャーの設立から精算をまでを経験したことで「企業は組織や人の能力を高める」ことを考えるべきと思うようになった。現場を良く理解できた10年だった。
●管理者行動診断:MBD
「管理者の能力レベルは?」「優秀な管理者とそうでない管理者の違いは?」「管理者一人ひとりの能力レベルは?」など、管理者の能力開発に役立てていただくためのアセスメントが「管理者行動診断」である。管理者に求められる能力を11のコンピテンシーから測定し、各コンピテンシーの現状を把握し課題を特定するものである。測定内容は「概念力」「遂行力」「影響力」の3カテゴリーおよび「生産性と充実感」である。
●現在の取り組み
セールス分野、マネジメント分野、サービス分野、共通プログラムに加え能力アセスメントツールを充実させている。あらゆるニーズに応えるべく、公開講座も充実させている。また、2010年8月には社内にセミナールームを開設し、様々な分野で皆様の課題解決のお手伝いができればと考えている。
16:55~ 花の祈り〜 涼恵 様
 ●世界でたった一人の神職の唄ひ手であり、その音楽、世界観も独特の空気感が漂い、オーラを放っていた。また、押し花で彩られた照明が彼女の神々しさをより一層惹きたてており、幻想的な世界に会場が包まれた。
●世界でたった一人の神職の唄ひ手であり、その音楽、世界観も独特の空気感が漂い、オーラを放っていた。また、押し花で彩られた照明が彼女の神々しさをより一層惹きたてており、幻想的な世界に会場が包まれた。






 ブラジルは移民の国である。「人種の坩堝」と言われるがごとく世界中から人が集って「ブラジル」という国を作っている訳だから、この国の社会そのものがグローバルであり、日々の普段の生活がグローバルである。何しろ、隣の主人はイタリア人、そのまた隣はポルトガル人、前はシリア人、それぞれの奥さんはまた別の国、という訳である。しかも、これらが混血すると何人なのか解らない、すべてブラジル人。
ブラジルは移民の国である。「人種の坩堝」と言われるがごとく世界中から人が集って「ブラジル」という国を作っている訳だから、この国の社会そのものがグローバルであり、日々の普段の生活がグローバルである。何しろ、隣の主人はイタリア人、そのまた隣はポルトガル人、前はシリア人、それぞれの奥さんはまた別の国、という訳である。しかも、これらが混血すると何人なのか解らない、すべてブラジル人。 キャタピラー九州株式会社 営業部 販売促進課 後藤 悦夫さま
キャタピラー九州株式会社 営業部 販売促進課 後藤 悦夫さま <新規事業への取組み> キャタピラー九州では、教習事業や営農環境事業という新規分野に進出することで、コアビジネスである建設機械事業をサポートし、かつ各事業が独自で売上拡大、収益向上できることを目指しています。キャタピラー九州に相談すれば何でも答えてくれるとお客さまに思って頂くためにも今後も力を入れて取り組んで参ります。
<新規事業への取組み> キャタピラー九州では、教習事業や営農環境事業という新規分野に進出することで、コアビジネスである建設機械事業をサポートし、かつ各事業が独自で売上拡大、収益向上できることを目指しています。キャタピラー九州に相談すれば何でも答えてくれるとお客さまに思って頂くためにも今後も力を入れて取り組んで参ります。 前回(2010年2月)に続き、今回は教育担当者として新人に〝いかに学ばせるか〟について考えたい。学ばせるためのコツは3つある。1つ目は「手本になること」である。何かを教わると、新人はまずは頭で理解する。その上で、手本である我々教育担当者を見て、「どこまでやったらよいか」の程度を考える。
前回(2010年2月)に続き、今回は教育担当者として新人に〝いかに学ばせるか〟について考えたい。学ばせるためのコツは3つある。1つ目は「手本になること」である。何かを教わると、新人はまずは頭で理解する。その上で、手本である我々教育担当者を見て、「どこまでやったらよいか」の程度を考える。 「士は節義をたしなみ申すべく候
「士は節義をたしなみ申すべく候 イオン九州株式会社 ストアサポート本部教育訓練部 マネージャー中村正様
イオン九州株式会社 ストアサポート本部教育訓練部 マネージャー中村正様 ラーニング・システムズとは、マネジメント層に対し、特に「部下と良好な関係を構築するためのコミュニケーション手法」について研修を依頼しています。部下一人ひとりに合わせたサポート法など、実際の現場でのケースを使うため効果が期待できます。
ラーニング・システムズとは、マネジメント層に対し、特に「部下と良好な関係を構築するためのコミュニケーション手法」について研修を依頼しています。部下一人ひとりに合わせたサポート法など、実際の現場でのケースを使うため効果が期待できます。 2010年がスタートして既に半月が経過した。雇用環境が厳しい中、採用人数が不確定なまま各企業の採用担当者は2011年度の新卒採用活動を本格化している。“業績の見通しが厳しいから採用をストップする”では将来的に年齢構成の歪みが生じてしまい組織力の低下につながる恐れがある。将来への投資として新卒採用を継続する企業も多いと思われるが、折角採用した新入社員を効果的に育成し、早い段階で社会人としてかつビジネスマンとして戦力化していくことが採用担当者・教育担当者の導入教育の目的であろう。 教育カリキュラムに沿って、社内講師で実施する企業も多くなってきたが、効果的な指導の仕方やいかに学ばせるかについて、考えてみたい。
2010年がスタートして既に半月が経過した。雇用環境が厳しい中、採用人数が不確定なまま各企業の採用担当者は2011年度の新卒採用活動を本格化している。“業績の見通しが厳しいから採用をストップする”では将来的に年齢構成の歪みが生じてしまい組織力の低下につながる恐れがある。将来への投資として新卒採用を継続する企業も多いと思われるが、折角採用した新入社員を効果的に育成し、早い段階で社会人としてかつビジネスマンとして戦力化していくことが採用担当者・教育担当者の導入教育の目的であろう。 教育カリキュラムに沿って、社内講師で実施する企業も多くなってきたが、効果的な指導の仕方やいかに学ばせるかについて、考えてみたい。 「敵艦見ユトノ警報ニ接シ、聯合艦隊ハ直ニ出動、之ヲ撃滅セントス、本日天気晴朗ナレドモ波高シ」明治38年(1905年)5月27日午後、朝鮮半島南東岸鎮海湾の連合艦隊旗艦「三笠」から東京の大本営あてに発せられた電文である。起草したのは秋山真之。そしてZ旗を掲げ、東郷平八郎司令長官から全艦隊の将士に告げられる「皇国ノ興廃此ノ一戦ニアリ、各員一層奮闘努力セヨ」、この電文を読んだだけで身震いするような高揚感を覚え、日本人として凛とした気持ちになる。
「敵艦見ユトノ警報ニ接シ、聯合艦隊ハ直ニ出動、之ヲ撃滅セントス、本日天気晴朗ナレドモ波高シ」明治38年(1905年)5月27日午後、朝鮮半島南東岸鎮海湾の連合艦隊旗艦「三笠」から東京の大本営あてに発せられた電文である。起草したのは秋山真之。そしてZ旗を掲げ、東郷平八郎司令長官から全艦隊の将士に告げられる「皇国ノ興廃此ノ一戦ニアリ、各員一層奮闘努力セヨ」、この電文を読んだだけで身震いするような高揚感を覚え、日本人として凛とした気持ちになる。
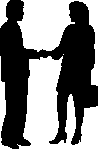 営業を取り巻く環境は厳しい。市場は冷え込み、各企業においても現状の生産性向上やコストダウンは考えても、新たに設備投資や新事業を行うことは困難である。そのような状況の中で、営業担当者は今どのような活動をすべきなのだろうか。
営業を取り巻く環境は厳しい。市場は冷え込み、各企業においても現状の生産性向上やコストダウンは考えても、新たに設備投資や新事業を行うことは困難である。そのような状況の中で、営業担当者は今どのような活動をすべきなのだろうか。 ~お客さまに付加価値を提供できる営業マンの育成~
~お客さまに付加価値を提供できる営業マンの育成~ ラーニング・システムズ社とは2007年より、直売営業経験の比較的短い営業マンを中心として「営業スキルの基本を修得する」ことを目的に研修を実施しています。そろそろ営業の壁にぶち当たる時期に、お客さまの立場に立った営業プロセスを学び、お客さまをじっくり観察し、相手のニーズに合わせた営業活動を展開する、石油オンリーから脱石油を目指した今後の営業活動には不可欠のスキルです。研修の実施は参加者からの感想を重視して検討しますが、評判は良好です。ラーニング・システムズ社には、今後より実践的で成果が見える内容の営業力強化研修を期待しています。
ラーニング・システムズ社とは2007年より、直売営業経験の比較的短い営業マンを中心として「営業スキルの基本を修得する」ことを目的に研修を実施しています。そろそろ営業の壁にぶち当たる時期に、お客さまの立場に立った営業プロセスを学び、お客さまをじっくり観察し、相手のニーズに合わせた営業活動を展開する、石油オンリーから脱石油を目指した今後の営業活動には不可欠のスキルです。研修の実施は参加者からの感想を重視して検討しますが、評判は良好です。ラーニング・システムズ社には、今後より実践的で成果が見える内容の営業力強化研修を期待しています。






